
ネオラボ
- 【業務内容】
- ラボ型オフショア開発事業
- 【利用用途】
- 見積管理、請求管理、購買管理など


人材関連事業を中心に創業したネオキャリアグループが、ヘルスケアやBPOなどの分野に領域を拡大していく中、グループ全体のIT導入・構築・運用を手がけつつ、ベトナムでのラボ型オフショア開発を急速に拡大しているのが株式会社ネオラボ(以下、ネオラボ)だ。
2015年にネオラボは創業し、急速に事業が拡大。事業の拡大に合わせシステムを導入することになったが、”組織変更を柔軟に行う”というグループの特性から「グループ内のバックオフィスの変更に柔軟に対応できる」ことが必須要件であった。それを満たすものとして採用されたのがkintoneだ。
今回は、取締役社長 大川智弘氏と、2016年新卒ですぐに事業企画部に配属され、チームリーダーとしてkintone アプリ開発を担当している中岡直輝氏に、kintone導入の背景やアプリ開発に関するお話をうかがった。
2015年に約10人のスタッフで創業したネオラボは、「新しいものはとりあえず触ってみる」という大川氏のスタンスのもと、自社開発のビジネスコミュニケーションプラットフォームの拡販を中心に、ドローン、AR、VRなど、先進的な分野でも実績を上げ、設立当初から急成長を遂げていった。
「もともとネオキャリア本体のIT領域を担当する部署からスタートしました。その段階で既に10人のチームを抱えており、バックオフィスを私1人で回せるような業務量ではなく、破たんするのが目に見えていました。また、業務拡大に合わせて人材を増やすビジョンでしたが、人材が増えるに比例して管理の人間が増えるのは避けたかったのです。
そこでバックオフィスをシステム化することになったのですが、グループの特性として『部署を作った、解体した』というような組織変更が頻繁に行われていました。また、新しいテクノロジーを使った商材を半ば「勝手に作る」といったこともあり、導入するシステムにはかなりの柔軟性を求めていました。その柔軟性のことを私はよく“グニョグニョしたシステム”と表現していました。」(大川氏)
また、グループ全体の業務フローを完全には把握できていない状況からのスタートであったことも、柔軟性を強く求める背景だった。さらに、スタッフが増えればワークフローによる電子稟議を加えることも必要になる。事業のスケールに合わせた柔軟なシステム構築をどのように行うのか。この課題を解決するために大川氏が注目したのがkintoneであった。

取締役社長 大川 智弘 氏
前職でkintoneを活用していた大川氏は、“グニョグニョ”したシステム構築にはkintoneが適しているという実感を既に持っていた。
「最初に手を着けたのが、グループ内で見積書をプロセス管理で承認後、PDFで自動発行する『見積書アプリ』でした。ちょうど新卒で配属されてきた中岡君に『見積書を作るアプリをよろしく』と振ったのですが、新卒ということもあり、まず『見積書とはなんぞや』というビジネス的な指導も必要でした。ただ、それ以前の問題に頭を抱えることになりました・・・」(大川氏)
「実は学生時代からほとんどパソコンには触れていなかったので、kintoneはおろかExcelの使い方もわからないし、そもそもタイピングすらできませんでした。大川さんには『え?そこから教えなきゃならないの?』と絶句されました。卒業研究もノートにまとめたものを学校の行き帰りの電車の中でスマホを使ってプチプチと書いて、あとからパソコンで体裁を整えたというくらいなんです。新卒の配属時に、新規事業領域の経営企画という点に魅力を感じてネオラボを志願し、約200人の新卒研修を経て念願のネオラボ配属を、勝ち取りました。しかし本当に1から学ばなければならない状態でした。正直な話、今でもExcelはよく分からず、他部署の同僚からExcel関数の話などを聞いても『あ、それはkintoneに置き換えるとこういうことかな?』というようにkintoneベースでの発想になってしまうのです。」(中岡氏)

事業企画部 チームリーダー 中岡 直輝 氏
タイピングすらできなかった中岡氏は、「見積書の業務上の位置づけ」を調べあげ、単に見積書を作るのではなく、“業務を円滑にするためには、どのような見積書が最適か”を考えた。時に大川氏にアプリの考え方やkintoneの使い方の指導を受け、ついに「見積書アプリ」は完成。その経験をもとに、プロセス管理を他部署と連携して利用できる「請求書アプリ」や、金額によって承認者を自動判断する「購買申請アプリ」など、グループ内向けのアプリを次々に開発することとなった。その数は1年で100アプリ以上にのぼる。
中岡氏はもはや“kintoneネイティブ”とも言える存在として、日々アプリの開発や改修に取り組んでいるのだ。
ネオラボだけでなく、ネオキャリア本体や他のグループ会社でもkintoneは採用されている。その為、本体やグループ会社から依頼を受け、アプリを開発するケースも多く、現在は依頼が殺到し「順番待ち」の状態だという。引く手あまたの状態だが、中岡氏はこういった依頼に応える度に、どんな要望にも柔軟に対応できるkintoneの強みを感じるとのこと。
「kintoneのいいところは、何でもできるということです。大川さんはよく小麦粉に例えて『パンにもなるし、パスタにもなるし、うどんにもなる』というように表現しますが、私は『紙粘土のようなもの』と説明することが多いですね。自由に形を変えて『こんなことをしたい』というニーズに合致したアプリを開発できるわけです。
もう1つ大きいのは、すぐに改修できるということです。業務の変更による改修の要望のほか、『ここが使いづらいから改良してほしい』といった要望など、多数寄せられてくるのですが、自分の手でその場で直せるのもいい点です。」(中岡氏)
こういった活動が功を奏したのか、グループ全体にkintoneは浸透し始め、大川氏によればグループ内に『 kintoneいいよね!』の波が来ているという。
「波が来ているといっても、kintoneを使いこなしているスタッフは、まだ多くはありません。今後は中岡君のようなkintoneネイティブを増やしていく必要があります。求人の際に優遇するスキルとして「kintoneを使える」というのを記載する段階にきているかもしれません。というのも、これまでは社内の業務改善が、kintone活用の主たる目的でしたが、今後は社外向けのビジネスにも活用したいと考えています。現在、グループ内の組織を横断して、社外に向けた『業務改善のチーム』の立ち上げを提案しています。グループ内で実績をあげているので、社外向けの提案もスムーズにできると考えています。」(大川氏)
「私は将来的に、kintoneを使った“業務改善”を専門とする職種の創出を目指したいと思っています。これまでになかった職種ですが、『kintoneを使えば、こんなに業務が楽になる』『こんなに効果があがる』ということを、広く伝えることができたらと考えています。」(中岡氏)
ネオラボのkintoneを広める取り組みは、今、社内だけでなく社外にも目を向けはじめており、大きな転換点に差し掛かっている。この取り組みは、kintoneの認知を高めるだけでなく、中岡氏のような“kintoneネイティブ”の拡大にも繋がる非常に面白い取り組みである。今後のネオラボの活動に目が離せない。
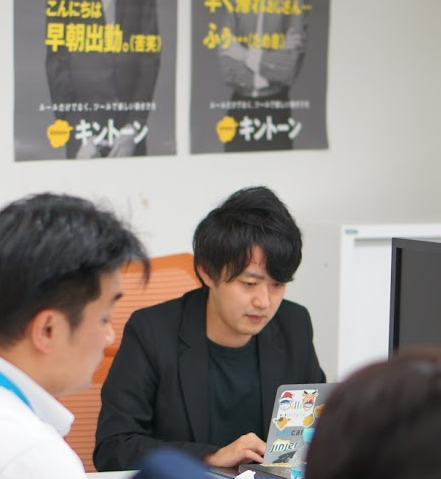
本動画に関する著作権をはじめとする一切の知的財産権は、サイボウズ株式会社に帰属します。
kintoneを学習する際、個人や社内での勉強会のコンテンツとしてご利用ください。
データを変形 ・加工せず、そのままご使用ください。
禁止事項
ビジネス資料や広告・販促資料での利用など
商用での利用は許可しておりません。