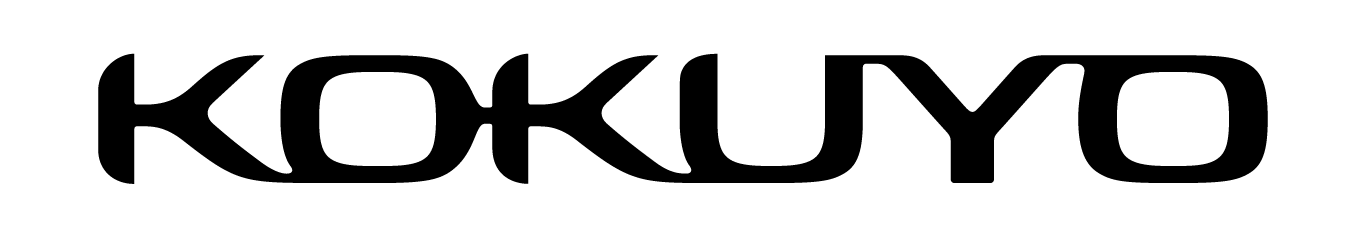
コクヨ
- 【業務内容】
- ステーショナリー事業 / ファニチャー事業 / 通販・小売事業
- 【利用用途】
- 請求管理 / ワークフロー
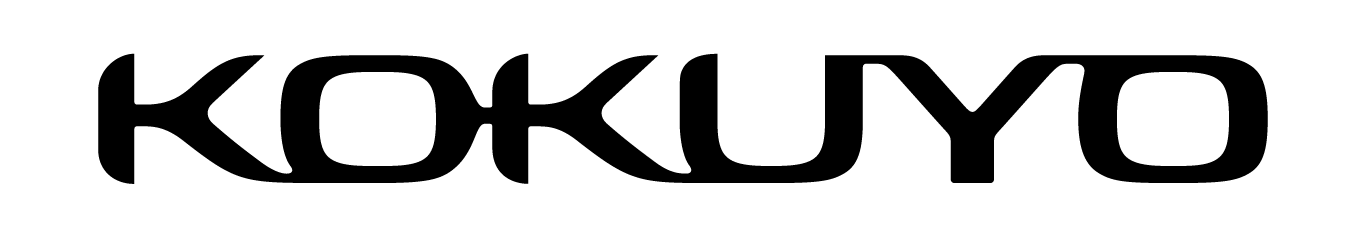


文具や家具のみならず、ワークスタイルおよびライフスタイル領域に必要なソリューションを幅広く提供するコクヨ株式会社。同社のビジネスサプライ事業本部では、テクノロジー活用によるビジネス変革を推進しており、非エンジニアでも日々の業務改善につながるアプリを開発できる基盤として、サイボウズのkintoneを採用しました。その経緯について、ビジネスサプライ事業本部 Bサプライシステム本部 本部長 内田 一雄氏、同本部 開発ユニット システム2G 岩坂 真奈氏および同G 池谷 和実氏にお話を伺った。
和式帳簿の表紙を製造する「黒田表紙店」として1905年に創業、現在は「be Unique.」を企業理念に掲げ、文房具やオフィス家具、通信販売に至るまで事業の多角化を進めているコクヨ株式会社。ワークスタイル領域とライフスタイル領域の2つの事業領域でビジネスを展開しており、文具や家具のみならず、豊かな生き方を創造する企業になることを目指している。顧客体験価値の拡張を成長戦略に掲げた「長期ビジョンCCC2030」の達成に向けて、現在はモノ×コトによる既存事業のさらなる成長と収益性の向上に向けた体験価値拡張戦略を強力に推し進めている。
同社において、Eコマースプラットフォームとして多くの企業に活用されている「カウネット」および「べんりねっと」を中心にビジネスを展開するビジネスサプライ事業本部では、テクノロジーを生かして事業変革を進めていくことを大きな方向性として掲げている。そのためには、ITの知見を持つエンジニア人材とともにECのような重要システムを磨き上げていく取組み、さらに現場の業務改善をサポートするためのツール、そして企業全体のIT戦略が重要となると内田氏は説明する。「これら3つのどれか1つでも欠けてしまっては、テクノロジーで事業変革を成し遂げることが難しい。特に現場の業務改善ツールに関しては、これまでOfficeアプリケーションをはじめPC内に閉じた環境での利用が中心で、どうしても情報が分散してしまい、プロセス自体も属人化してしまう。それらをうまく解消していくための基盤が必要だと考えたのです。」

ビジネスサプライ事業本部 Bサプライシステム本部 本部長 内田 一雄氏
加えて、事業部門の非エンジニアであっても自ら主体的にシステム開発できる、IT活用のハードルを下げていけるような環境づくりも求められたのだ。「ITが難しいと感じてしまうメンバーであっても、簡単に開発できる体験を通じて、ITをビジネススキルとして「あたりまえのように」理解できるような環境づくりを目指したのです」と内田氏は語る。そのためには、専門知識がなくとも業務改善につながるアプリ制作が可能なノーコードツールに注目したとkintone導入のきっかけを語る。
実は、すでに全社で別のノーコード開発ツールを導入していたものの、使い方の面で非効率な運用が続いていたという。「私たちの使い方に問題があった部分もありますが、一部の請求書発行業務で言えば、Excelで作成した依頼書を承認プロセスに乗せ、経理部門側でそのExcelをダウンロードしてAccessに転記、その後別の仕組みと連携させるといった、やや煩雑な手作業が発生していました。利用者の立場としても効率的ではないと感じていたのです」と岩坂氏は当時を振り返る。業界における特殊な処理の場合、基幹システムではサポートできないことから手作業での処理が多く発生しており、従来のツールでは改善策が実施しづらい状況だったのだ。
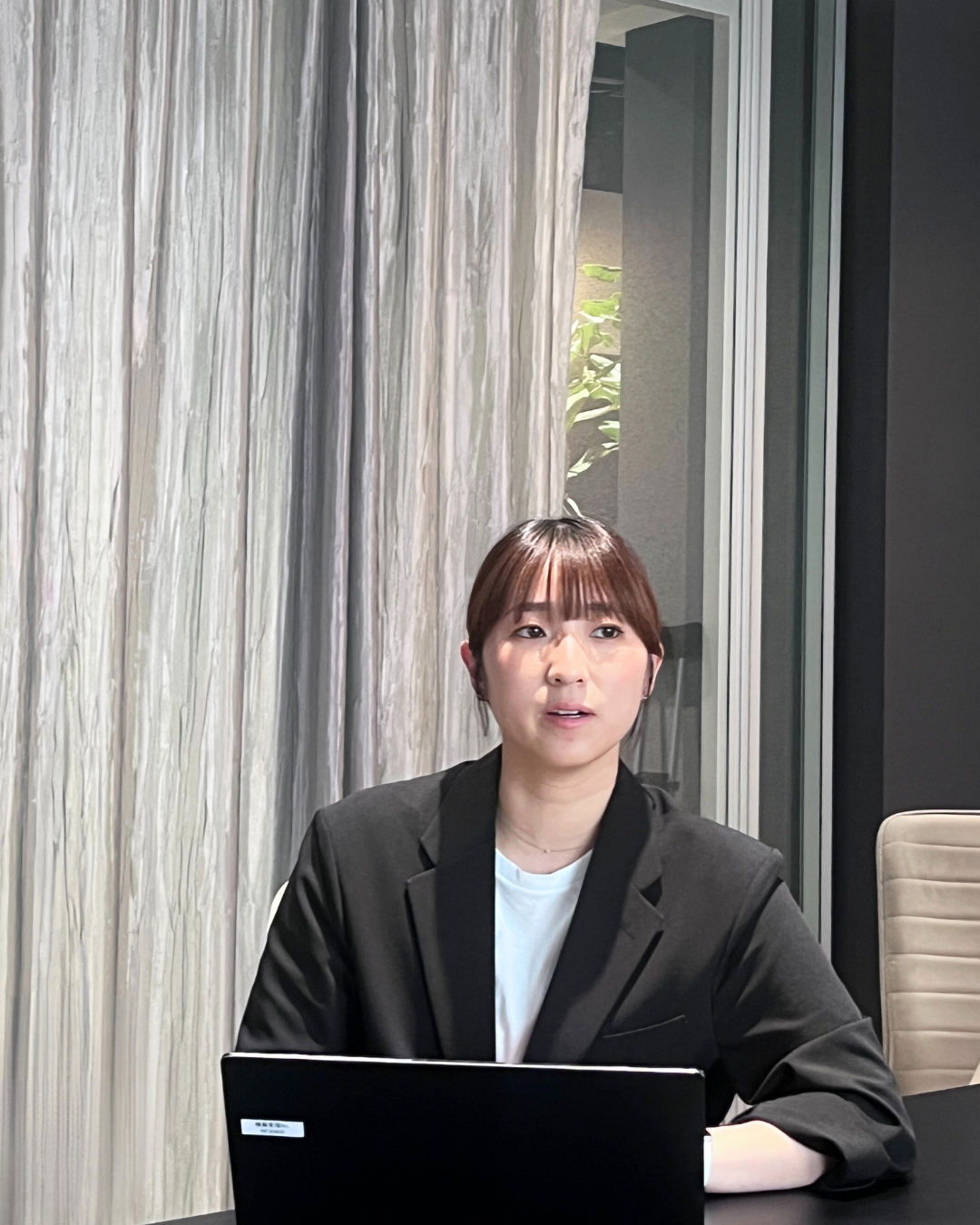
ビジネスサプライ事業本部 Bサプライシステム本部 開発ユニット システム2G 岩坂 真奈氏
新たな環境づくりでは、非エンジニア人材であっても開発しやすいノーコードツールを中心に検討し、市場において多くの実績を持っていたkintoneに着目したという。「クラウドサービスだけに試しやすく、実際に触って開発してみてもらいやすいことから、kintoneに注目したのです。従来のツールとは異なり、kintoneはDBの機能を持ちながら、プロセスドリブンなアプローチが可能です。その点でも、私たちが改善を進めていきたい課題に応えやすいと考えました」と内田氏。
既存のノーコード開発ツールと使い勝手の面で比較した岩坂氏だが、開発のしやすさに大きな違いがあったという。「導入済みのものと違い、kintoneは開発のためのナレッジがインターネットから入手しやすく、何かあればヒントが得られます。IT未経験の私にとっても、ハードルの違いを感じたのです」。また、お試し期間でkintoneに触れた時の印象として、「開発画面で必要なフィールドを置くだけでシンプルなアプリが作成できました。触り始めたときは複雑なことがどこまでできるか未知数でしたが、着手しやすさは間違いなくあると実感したのです」と当時の印象について岩坂氏は振り返る。
豊富なプラグインや導入事例が手に入りやすく、拡張性の面でも内田氏はKintoneを高く評価したという。内田氏は「シンプルな使い方だけでなく、プラグインを使えば高度なシステム化も実現できます。非エンジニアであっても拡張性の高い仕組みが活用できるのは大きなメリットです」と語った。
そこで、いったん最小単位でのライセンスをまずは契約し、kintoneを使った業務改善のアプローチをスタートさせることになったのだ。
現在は、営業やMD、経理をはじめビジネスオペレーションに関わるビジネスサプライ事業本部に在籍するおよそ7割にあたる260名ほどのメンバーがkintoneを活用しており、試作含めて90ほどのアプリが日々の業務を支えている。全社的には事業本部ごとに複数ドメインでkintoneを運用しているが、同事業本部内では1つのドメインで複数ユニットそれぞれが運用、各部署に点在する20名ほどにアプリ作成権限を付与し、それぞれ自走した形でアプリ開発が行われている。「基本的な動画を見たうえでkintoneの基礎知識を習得してもらい、ハンズオンのアーカイブ動画を視聴、自身で簡単なアプリを作成してもらった段階で権限を付与しています」と同ユニット システム2G 池谷氏は説明する。なお、開発ユニットではkintoneのカスタマイズを支援するgusuku Customineやkintone内の情報をもとにメール送信が可能なkMailer、複数プラグインが活用できるATTAZoo+などのプラグインを主に活用している。

ビジネスサプライ事業本部 Bサプライシステム本部 開発ユニット システム2G 池谷 和実氏
開発ユニットが作成したアプリの具体例は、基幹システムでは対応できない一部特殊な請求書発行業務に関する請求書発行アプリだ。請求書発行に必要な情報を業務部門メンバーが起票すると、事前に設定されたワークフローに沿って申請承認プロセスが進み、最終的に経理部門側で承認した段階で請求書発行ボタンが表示される。gusuku Customineによって事前に設定されたフォーマットにて請求書が作成され、その後kMailerを使って取引先にメール配信される流れだ。「値引きやキャンペーンといった、汎用的な基幹システムでは対応できない特殊な相殺処理が必要な請求処理に対応するため、相殺処理に関する情報を扱うアプリを作成しています。この処理を親アプリとして登録し、部内に共有したい情報と請求処理に必要な情報をそれぞれ子アプリとして連携させています。1度の情報入力で2つの業務にうまく連携できる状態を作りました」と池谷氏は説明する。
また営業部門にある業務改善グループでは、従来Google スプレッドシートで集めていた現場の課題をkintoneにて収集するアプリを作成しており、集まった情報のなかでシステムのエンハンスが必要になる案件に関しては、情報システム部門が案件管理アプリに展開。コスト管理とともに、課題管理から変更管理、リリース管理といった、計画的かつ安全に進めるための仕組みとしても、プロセス管理にもkintoneを役立てている。
同事業本部では、利用者の10%弱がアプリ開発権限を有しているが、開発メンバーをさらに増やしていくべく、アンバサダー活動を積極的に展開。「アンバサダーとして活動して欲しい人や自ら手を挙げていただいたメンバーにアカウントを付与し、約6000名のグループ社員に成功事例などの情報発信やTIPSなどの情報共有を行っています。社内メンバーから直接相談いただく機会も増えています」と池谷氏。
なお、アンバサダーとの間で2週間に1度進捗確認のミーティングを実施しているが、「進捗報告などを記録していくアンバサダー管理アプリは30分かからず作成できました。シンプルなものなら、一瞬でアプリが作成できてしまいます」と岩坂氏はその実績を披露する。
kintoneを導入したことで、毎月100件を超える特殊な請求書処理業務に必要だった経理部門の工数が92%減と大幅な効率化を実現している。「従来はダウンロードしたExcelの情報を転記して、会計システムなど他システムへの展開するために多くの時間がかかっていました。今は現場からの申請に対して承認し、会計に投入するためのフォーマットにkintoneにて変換して投入するだけ。圧倒的な工数削減につながっています」と岩坂氏は評価する。
業務プロセスの可視化によって属人化の解消や業務の持続力向上に役立つことはもちろん、自動化によるガバナンス強化や現場部門でのアプリ開発者やアンバサダー増加によるテクノロジーの浸透にkintoneが大きく貢献している。「現状はプロセスの可視化によって属人化を排除する効果が中心ですが、いずれは蓄積されたデータを活用していくことも十分考えられます。別途基盤としてあるDWHをはじめとしたアナリティクスにおけるデータ活用に向けた連携は期待できるところです」と内田氏。現状マイクロサービスとして個別にある仕組みを連携させていくことは今後の検討課題となっている。
また、業務プロセスに立脚して非エンジニアであってもアプリ作成可能な環境が整備でき、ある意味で岩坂氏や池谷氏をはじめ、アンバサダーの取り組みが社内における大きな成功体験になっていることは何よりの効果だと内田氏は見ている。「ITツールの進化もそうですが、プロセスを変えるというビジネスパーソンとしてのマインドが醸成できていることがとても大きい。」
kintoneについては、「開発しやすいだけでなく、業務部門の人に説明するときも簡単に作成できることに驚きの声が挙がることも。導入してよかったというのが正直な感想です」と岩坂氏。kintone学習についても、世の中に動画などが多く出回り、ナレッジへもアクセスしやすいと好評だ。池谷氏は「最初に小さく始めてもアジャイル的に変えていけるため、ニーズに合わせて改修しやすいのがとてもいいポイント。ポータル画面にキャラクターを表示させるなど、使う人に触れてもらえるよう工夫しやすい」と評価する。レコードごとにコメントでコミュニケーションが図れる点も、kintoneが持つ大きな魅力の1つだと評価する。
今後については、引き続き事業本部内でkintoneの啓蒙活動を続けていきながら、デジタル技術を駆使して業務変革を推し進めていきたいという。「具体的な例でいえば、請求書とは別に管理している仕入伝票に対して、請求書の紙データを貼り付けて管理する別システムを運用しています。仕入伝票の備考欄にkintoneで作成した請求書番号を貼り付けておけば、内部監査時に情報確認しやすくなるはず」と池谷氏は期待を寄せている。コミュニケーション基盤として全社で定着しているSlackやRPAとの連携も含め、kintone活用をさらに推し進めていきたいという。
岩坂氏は“全社員を開発者にする”という大きな目標を掲げている。「何かあれば“kintoneでできるよね”がすぐに頭に浮かぶようになり、簡単にkintoneで実現できることが現場にひろがることが理想だと考えています。今は開発するとなると私たちのほうに問い合わせがきますが、現場同士で作っていけるようになれば私たちも現場もハッピーになる。そんな環境づくりに向けて、現場の皆さんをサポートしていきたい」と岩坂氏は意気込む。
IT人材の育成や生成AI連携といった取り組みはもちろんのこと、基幹系システムやサプライチェーン、チャネル系の仕組みがAWS中心にクラウドリフトしている同社だけに、kintoneとAWSとの連携も強化していきたいという。「システム間連携がますます重要になってきますし、現場からのニーズも高くなっています。既存の仕組みを変更せず、kintone側で個別のプロセスを回して基幹システムに返すといったことも含めて、AWSとの柔軟な連携は進めていきたい」と内田氏。特に業務の基幹となるシステムから外れるところをkintoneで可視化していき、さらにそのプロセスを経て基幹システムも含めて全体設計し直すなど、業務基盤全体の好循環をkintoneで生み出していきたいと今後について内田氏に語っていただいた。
本動画に関する著作権をはじめとする一切の知的財産権は、サイボウズ株式会社に帰属します。
kintoneを学習する際、個人や社内での勉強会のコンテンツとしてご利用ください。
データを変形 ・加工せず、そのままご使用ください。
禁止事項
ビジネス資料や広告・販促資料での利用など
商用での利用は許可しておりません。